 こんにちは。晴田そわかです。
こんにちは。晴田そわかです。
今回の記事では《【小学生・中学年向け】社会科の授業開きにぴったり!盛り上がる導入ゲーム10選》について紹介させて頂きます。
- はじめに:授業開きは、社会科のイメージをつくる大切な時間
- 社会科の導入にゲームを取り入れるメリット
- ① 社会科クイズビンゴ
- ② これはどこのマーク?ロゴ当てゲーム
- ③ 町たんけんすごろく
- ④ 社会科〇✕クイズ
- ⑤ だれが働いているでしょう?クイズ
- ⑥ 社会の宝探しクイズ
- ⑦ 地図記号ジェスチャーゲーム
- ⑧ 都道府県さがしゲーム
- ⑨ 社会かるた
- ⑩ 未来のまちアイディア会議
- まとめ:社会科が“好きになる”導入で、1年間のワクワクを仕掛けよう!
はじめに:授業開きは、社会科のイメージをつくる大切な時間
新学年、最初の授業——子どもたちはちょっぴり緊張しながらも、「どんな先生?」「この教科って楽しいのかな?」とワクワクしているものです。特に中学年(3・4年生)の子どもたちは、知的好奇心もぐっと高まってくる時期。社会科に「楽しそう!」「もっと知りたい!」という第一印象を持ってもらうには、導入の工夫が大切です。
今回は、そんな授業開きにぴったりの「社会科ゲーム」を10個ご紹介します。どれも簡単な準備ですぐに実践可能な内容ばかり。ゲームのあとは、そのまま学習内容にスムーズにつなげることができます。
社会科の導入にゲームを取り入れるメリット

「遊びから入るのってどうなの?」と思われる方もいるかもしれません。でも、導入ゲームには以下のような効果があります。
-
子どもたちの緊張が和らぎ、教室の雰囲気が温まる
-
社会科に対する“興味の芽”を育てる
-
自然な形で学習内容への橋渡しができる
-
みんなで楽しむことで、クラスの一体感も生まれる
中学年の子どもたちは、遊びを通して物事の意味を理解するのがとても得意な時期。ここからは、すぐに使える10のゲームを具体的に紹介していきます!
① 社会科クイズビンゴ

「ビンゴ」×「社会科クイズ」の組み合わせで、学びながら盛り上がれる人気ゲームです。
ゲームの概要・方法
-
あらかじめ用意した社会科クイズ(10~15問ほど)を出題します。
-
子どもたちは、9マス(または16マス)のビンゴカードに、答えとして使われそうな言葉を自由に記入。
※例:郵便、信号、川、工場、地図、など -
クイズに答えて、当たっていればそのマスに〇をつけていきます。
-
ビンゴになったら手を挙げて報告!
活用のコツ
-
出題内容は、3年生なら「身の回りの施設」、4年生なら「都道府県・特産物」などに調整可能
-
最後に「今日覚えた言葉で調べてみたいもの」を書かせると、自然な振り返りになります
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | ビンゴカード(白紙マス)、クイズ問題(口頭orプリント) |
| 所要時間 | 約15~20分 |
| ねらい | 社会科用語やテーマに親しむ/言葉への関心を高める |
🔍 ワンポイントアドバイス:
「自分で答えを予想してビンゴカードに記入する」ステップが、考える力を刺激します。クイズの出し方は少しオーバーに演出してOK! 盛り上がりますよ!
② これはどこのマーク?ロゴ当てゲーム

子どもたちが日常で見かけている「社会のマーク」を題材にした、視覚的にも楽しいクイズです。
ゲームの概要・方法
-
郵便局、交番、消防署、ゴミ収集車、非常口、車いすマークなどをスライドやプリントで提示。
-
「これは何のマーク?」と子どもたちに答えてもらいます。
-
正解と一緒に、どうしてそのマークが使われているのかも補足すると学びが深まります。
-
チーム戦にして「〇問正解で勝ち!」などのルールを加えると白熱します。
活用のコツ
-
身近な施設に関する単元(3年生)とリンクさせるとGOOD
-
実物写真+イラストのセット提示で理解度UP
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | マーク画像(スライド・プリント)/チーム戦の場合は得点表など |
| 所要時間 | 約10~15分 |
| ねらい | 社会の中にある記号・サインへの関心を高める/身近な施設に目を向ける |
🔍 ワンポイントアドバイス:
写真だけでなく、実際の生活の中でのエピソードを交えるとより印象に残ります(例:「先生はこのマークを駅で見つけたよ」など)。次の時間に「マーク探し」の宿題にしてもいいですね。
③ 町たんけんすごろく

社会科でおなじみの“町探検”をすごろく形式で疑似体験できるゲーム。中学年にぴったりの探究心をくすぐる活動です。
ゲームの概要・方法
-
「町のすごろくマップ」(例:学校→郵便局→スーパー→消防署など)をあらかじめ用意。
-
サイコロをふって、止まったマスに書かれたクイズやミッションに答えます。
例:「スーパーにはどんな仕事をしている人がいる?」「次の建物はどれ?」 -
クリアできればそのまま進み、できなければ1回休み、などのルールを決めておく。
活用のコツ
-
グループ対抗にすることで、自然と相談・対話が生まれます
-
単元の導入だけでなく、まとめにも使えます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | すごろくマップ(手作りでもOK)、サイコロ、駒(色付きボタンなど) |
| 所要時間 | 約25~30分 |
| ねらい | 地域の施設や役割を楽しみながら学ぶ/町に関心をもつ |
🔍 ワンポイントアドバイス:
クイズに「子どもたちの学校の周辺施設」に関する内容を盛り込むと、一気に“自分ごと”に。発展として、自分たちで「すごろくマス」を作ってみるのもおすすめです!
④ 社会科〇✕クイズ

「えっ、うそ?」「ほんとに?」と声があがる〇✕クイズは、導入にぴったり!クラスの一体感も生まれます。
ゲームの概要・方法
-
「社会科に関する〇✕クイズ」を出題。(10問前後)
-
子どもたちは〇・✕カード、または手でポーズをとって答える。
-
正解数を記録していく形式にすると競争感が出て盛り上がります。
例題(3年向け)
-
郵便ポストは青色である。(✕)
-
消防車は赤色である。(〇)
-
ごみ収集車は毎日走っている。(✕)など
例題(4年向け)
-
愛知県では車を作っている会社がある。(〇)
-
りんごは北海道の特産物である。(✕)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | 〇✕クイズ(スライド・プリント)、〇✕カード(任意) |
| 所要時間 | 約10~15分 |
| ねらい | 社会的知識への興味を引き出す/基礎知識を確認する |
🔍 ワンポイントアドバイス:
「正解のあとにちょっとしたエピソードを話す」と、記憶に残りやすくなります。「郵便ポストは昔、黒だったんだよ」など、小ネタを用意しておくと◎!
⑤ だれが働いているでしょう?クイズ

職業と施設のつながりを考えるクイズで、社会の仕組みへの関心を高めます。
ゲームの概要・方法
-
各施設(例:郵便局、病院、工場など)で働く人のヒントを出します。
-
子どもたちはそのヒントをもとに、職業を当てます。
例:「お客さんの手紙を配達します」「白い服を着ています」 -
正解者にはポイントをあげるなど、簡単な競争要素も可。
活用のコツ
-
「だれか一人が働いている人になりきって話す」ロールプレイ形式にしても◎
-
働く人の気持ちにふれる導入にもなります
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | クイズ問題、なりきり用のセリフカード(任意) |
| 所要時間 | 約15~20分 |
| ねらい | 働く人と社会とのつながりを考える/職業への関心を育てる |
🔍 ワンポイントアドバイス:
「なりきりインタビュー」もおすすめ!「この仕事でうれしいときは?」「たいへんなことは?」などをロールプレイ形式で答えさせると、子どもたちの視野がぐっと広がります。
⑥ 社会の宝探しクイズ

教室を“探検の舞台”に変える体験型のゲーム。ヒントをもとに、教室内に隠された「社会クイズ」を探し出します。
ゲームの概要・方法
-
教室内に「クイズカード」を10〜15枚ほど隠します。カードには社会に関する問題が書いてあります。
-
子どもたちはペアやグループになって、教室を歩き回ってカードを探し、問題に挑戦します。
-
解答数を競ったり、正解でスタンプをもらったりして達成感を演出すると◎。
例題
-
赤い車で火事の現場に行く乗り物は?(消防車)
-
郵便ポストの色は?(赤)
-
地図記号で「川」を表すマークは?(3本線の記号)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | クイズカード、答え用紙、スタンプやシールなど |
| 所要時間 | 約20〜25分 |
| ねらい | 楽しみながら社会的知識を確認する/体を動かして集中力を高める |
🔍 ワンポイントアドバイス:
カードの裏に「ボーナスクイズ」や「先生からのヒントカード」を混ぜておくと、盛り上がり倍増!動きのある活動が好きな子に特におすすめです。
⑦ 地図記号ジェスチャーゲーム
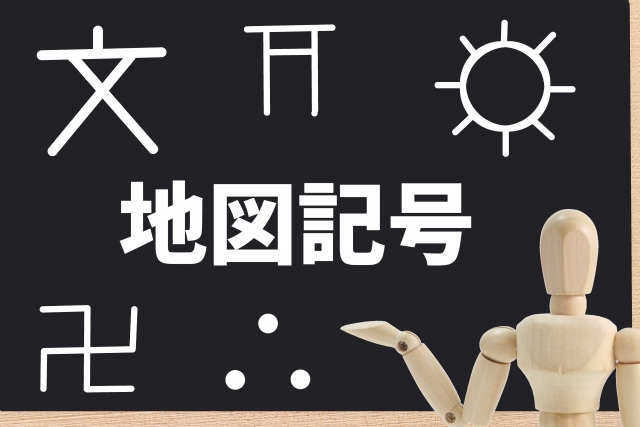
体を使って地図記号を表現!見て・当てて・笑って楽しいジェスチャーゲームです。
ゲームの概要・方法
-
代表者(子ども or 教師)が、くじで引いた地図記号を「体で表現」します。
例:木の形→手を広げて枝を表現、学校→帽子をかぶるしぐさなど -
見ている子どもたちは、それがどの地図記号かを当てます。
-
チーム対抗にするとさらに盛り上がります!
活用のコツ
-
地図記号がまだ分からない時期なら「ヒントつき」で!
-
見ている子にも「手がかりを言葉で説明してもらう」と、理解が深まります
🔍 ワンポイントアドバイス:
最初は教師が見本を見せるとやりやすいです。「体でやるのが恥ずかしい子」には、絵カードでのヒント係を任せてもOK!
⑧ 都道府県さがしゲーム

日本地図を使ったミニゲームで、都道府県の位置や名前に親しむ導入ゲームです。
ゲームの概要・方法
-
日本地図(大きめのもの)を提示し、「この県はどこでしょう?」クイズを出題。
-
指名された子どもが、該当する都道府県を地図上で指差します。
-
ヒントとして「〇〇県には富士山があるよ」など特徴を出すとわかりやすい!
応用編
-
チームに分かれて早押し形式にする
-
出された都道府県の「特産物」や「名所」を追加で調べさせる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | 日本地図ポスターまたは大型モニター、指し棒など |
| 所要時間 | 約15〜20分 |
| ねらい | 都道府県に関心を持つ/日本の地理に親しむ |
🔍 ワンポイントアドバイス:
「地元から一番遠い県はどこ?」「〇〇先生の出身県はどこ?」など、“身近なつながり”を入れると一気に興味が高まります!
⑨ 社会かるた
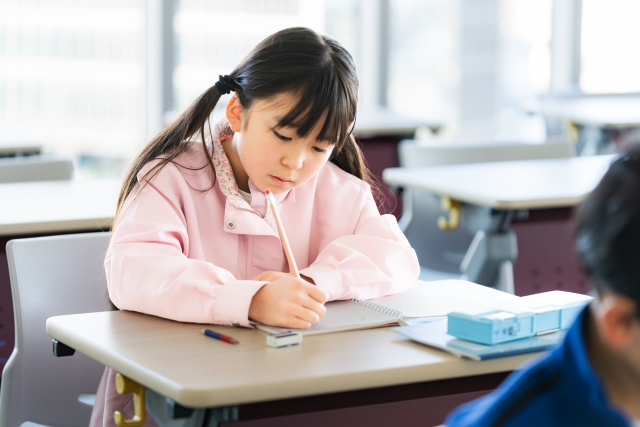
社会に関する用語や知識を使った「かるた遊び」で、楽しく知識を定着させるゲームです。地理・地図記号・仕事・歴史人物など、テーマを絞って実施するのがポイント!
ゲームの概要・方法
-
あらかじめ社会科に関する「読み札」「取り札」をセットで準備します。
-
読み手が札を読み、子どもたちは該当する取り札を取ります。
-
個人戦でも、チーム戦でもOK!読み札の読み上げを子どもが担当しても盛り上がります。
例:地図記号かるた
-
読み札:「本を読むならここに行こう」→ 取り札:「図書館の記号」
-
読み札:「非常時に助けてくれる人がいる建物」→ 取り札:「消防署の記号」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | 社会科かるた(市販 or 手作り)、机の上に広げられるスペース |
| 所要時間 | 約15〜25分 |
| ねらい | 社会科用語への関心を高める/集中力・瞬発力を育てる |
🔍 ワンポイントアドバイス:
読み札を子どもたちに作ってもらうと、後日にも活用できる教材に!「かるた制作授業」として発展的に扱えます。
⑩ 未来のまちアイディア会議

これからの社会をつくる“市民”としての第一歩!「未来の町をつくるならどんな施設・仕組みがあるといい?」を考えるグループワークです。
ゲームの概要・方法
-
4〜5人のグループで、「未来のまち」のテーマを設定(例:住みやすい町、災害に強い町)
-
地図や模造紙に「こんな建物がほしい」「ここに駅があると便利」などアイディアを出し合って町をデザイン。
-
発表タイムで、お互いのアイディアを共有します。
ヒントになる問い
-
スーパーはどこにある?
-
子どもが遊べる場所は?
-
災害が起きたときの避難所は?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | 模造紙、色ペン、シール、雑誌の切り抜きなど |
| 所要時間 | 約30〜40分(発表含む) |
| ねらい | 社会づくりの視点をもつ/協働して考える力を育てる |
🔍 ワンポイントアドバイス:
本格的な内容ですが、「発表は自由なポスター形式」「絵が苦手な子は説明役」と役割を分担すれば、どの子も活躍できます。初回は“夢いっぱい”の自由な町でOK!
まとめ:社会科が“好きになる”導入で、1年間のワクワクを仕掛けよう!

中学年の社会科は、「知っている世界を広げていく」第一歩。最初に「楽しい!」「もっと知りたい!」という気持ちを持たせることが、年間の学びの意欲につながります。
授業開きにゲーム的な要素を取り入れることで、子どもたちの表情がパッと変わり、社会に対する期待がグッと高まりますよ!
👩🏫 教師向けアドバイスまとめ:
-
活動の意味づけを大切に。「遊び」ではなく「学びにつながる楽しい導入」であることを、活動後に振り返らせる時間を取りましょう。
-
**どの子も参加できる工夫を。**勝ち負けより「発見」や「参加」に意味を持たせることで、学びの機会が広がります。
-
活動後に“ふりかえり”タイムを。「今日の活動で学んだこと」「面白かったこと」をノートに書いたり発言させたりすると、社会への視点がしっかり根づきます。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
記事の内容が、あなたの学級の社会科スタートを明るく・楽しく・深いものにするお手伝いになればうれしいです。気になるゲームがあれば、ぜひ次の授業で取り入れてみてくださいね!
✨関連記事はこちら⬇️