 こんにちは。晴田そわかです。
こんにちは。晴田そわかです。
今回の記事では《【小5・小6向け】算数の授業開きで盛り上がる頭脳ゲーム10選|考える楽しさを引き出す導入ネタ》について紹介させて頂きます。
- 算数で思考のウォーミングアップ!
- ① 数字のたし算パズル|ぴったり10をつくれ!
- ② ウソつきはだれ?数の条件ゲーム
- ③ ひらめきビンゴ|計算でビンゴを完成させろ!
- ④ はやく見つけろ!数の間違い探し
- ⑤ 答えはすべて「24」ゲーム|自由な発想でたどり着け!
- 🎓ワークシート:めざせ24! 4つの数字で答えをつくろう!
- ⑥ 算数なぞなぞリレー
- ⑦ チームで挑戦!パズル図形チャレンジ
- まとめ|算数は「考えるって楽しい」と感じることから
算数で思考のウォーミングアップ!
新学期の最初の授業、算数の教科書を開く前に、
「楽しい!」「もっと考えたい!」という気持ちを引き出したいですよね。
特に小学校高学年になると、論理的な思考やひらめき、試行錯誤の面白さにぐっと惹かれる子も多くなってきます。
そんな5年生・6年生の「心をつかむ」算数導入として、授業開きにぴったりな頭脳系ゲームを7つご紹介します。
どれも準備が簡単で、チームでも個人でも楽しめるアクティビティばかり。
算数の導入としてだけでなく、「思考のウォーミングアップ」としても活用できますよ!
① 数字のたし算パズル|ぴったり10をつくれ!

ゲーム内容
バラバラの数字カードから「和が10になる組み合わせ」を次々に見つけていくゲーム。制限時間内でいくつ作れるかを競います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | 1〜9の数字カード(人数分または班に1セット) |
| 所要時間 | 10〜15分 |
| ねらい | 組み合わせの力、加法の瞬発力、集中力を高める |
教師ワンポイントアドバイス:
最初は「ぴったり10」に限定して行い、慣れてきたら「ぴったり20」「ぴったり100(2ケタ加算)」にもチャレンジを。ペアで行うと会話も生まれ、思考も深まります!
② ウソつきはだれ?数の条件ゲーム
ゲーム内容
5人の「証言」から、誰か一人だけがウソをついていると仮定し、真実の数を推理するロジックパズルです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | プリントまたは黒板で出題 |
| 所要時間 | 15〜20分 |
| ねらい | 論理的な思考、条件整理、消去法のトレーニング |
例題:
「ある数字Xについて…」
-
A:Xは3より大きい。
-
B:Xは偶数だ。
-
C:Xは5より小さい。
-
D:Xは9の倍数だ。
-
E:Xは2けたの数だ。
「このうち1人だけがウソをついています。Xはいくつでしょう?」
教師ワンポイントアドバイス:
最初は全体で話し合いながら進めると、子どもたちの思考の進め方がわかります。「ウソが1人だけ」という条件が論理的思考をうながしますよ!
③ ひらめきビンゴ|計算でビンゴを完成させろ!
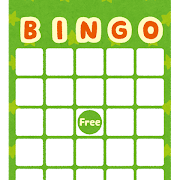
ゲーム内容
ビンゴカードに1〜50の数字を自由に書かせ、出題される計算問題の答えが一致すればマスが開けられるという形式。早くビンゴを完成させた人が勝ち!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | ビンゴカード(白紙)、筆記用具 |
| 所要時間 | 10〜15分 |
| ねらい | 四則計算への瞬発力、先を見越した配置の工夫、戦略的思考 |
教師ワンポイントアドバイス:
ただの運ゲームではなく、問題の難易度を調整したり、テーマ別に(偶数だけのビンゴなど)することで、学年や習熟度に合わせてアレンジできます!
④ はやく見つけろ!数の間違い探し
ゲーム内容
10個の計算の中に3つだけ「まちがい」があります。どこがどう間違っているかを見抜くスピードと正確さを競うゲーム。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | 計算ミス入りのプリントまたは黒板問題 |
| 所要時間 | 10〜12分 |
| ねらい | 計算の見直し力、観察力、説明力の育成 |
例:
-
23×4=92(○)
-
12×3=26(×)
-
45÷5=9(○)
-
16×2=34(×) など
教師ワンポイントアドバイス:
「どこが間違いか」だけでなく、「どう直せば正解になるか」まで説明させると、思考の言語化の練習にもなります。子どもが出題者になる形式も盛り上がります!
⑤ 答えはすべて「24」ゲーム|自由な発想でたどり着け!

ゲーム内容
指定された4つの数字を使い、四則演算を自由に組み合わせて答えを24にするパズルゲーム。
カードゲーム「24ゲーム」のアレンジで、紙とペンがあればOK!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | 数字カードまたは黒板に問題を書く、筆記用具 |
| 所要時間 | 10〜15分(慣れれば1問2〜3分でテンポよく) |
| ねらい | 数の操作、計算式の組み立て、柔軟な発想力 |
例題: 「3, 3, 8, 8 を使って 24 にしよう」
→ 解答例:8 ÷ (3 - 8 ÷ 3) = 24
教師ワンポイントアドバイス:
「解けたら前に出て発表→次の問題へ」というテンポのある進行がおすすめです。
ヒントは段階的に(①「掛け算がポイントかも?」など)与えるとクラス全体で学び合えます。
🎓ワークシート:めざせ24! 4つの数字で答えをつくろう!
◆ねらい
・四則演算の柔軟な使い方を学ぶ
・複数の式の組み合わせを試す中で、数の関係に気づく力を育てる
・自分の式を説明する力を育む
ルール
-
各問題にある 4つの数字をすべて1回ずつ使って、
「たし算、ひき算、かけ算、わり算」を自由に組み合わせ、答えを24にしてください。 -
数字の順番は変えてもOK。かっこ()を使ってもOK。
-
解けたら、自分の式を書いて、**「工夫したところ」や「ポイント」**をメモしよう!
| No. | 数字(4つ) | 式(自分で考えて記入) | 工夫・ポイントメモ |
|---|---|---|---|
| ① | 3, 3, 8, 8 | ||
| ② | 6, 6, 2, 2 | ||
| ③ | 4, 4, 7, 1 | ||
| ④ | 5, 5, 5, 1 | ||
| ⑤ | 2, 3, 4, 6 | ||
| ⑥ | 1, 3, 4, 6 | ||
| ⑦ | 7, 2, 2, 3 |
✅ チャレンジタイム!
-
ひとつの問題に 答えが何通りもあることも! 友達と見せ合ってみよう。
-
難しいときは「かけ算が必要?」「先にわり算を使ったら?」と考え方を変えてみてね。
🔍先生のコメント記入欄(使う場合)
📝教師用メモ(裏面などに)
正解例(複数あるうちの一例)
-
①:8 ÷ (3 - 8 ÷ 3) = 24
-
②:(6 ÷ (2 - 6 ÷ 2)) = 24
-
③:4 × (7 - (4 - 1)) = 24
-
④:(5 + 5 + 5) × 1 = 15(※こちらは24にはならない→「できない例」でも可)
-
⑤:(6 × 4) + (3 × 2) = 24
-
⑥:6 × (4 + 1) - 6 = 24(工夫パターン)
-
⑦:(7 × 3) + (2 ÷ 2) = 24
⑥ 算数なぞなぞリレー

ゲーム内容
チームで順番に算数なぞなぞに答えながら、ゴールを目指す形式のアクティビティ。
答えると次の子にバトンタッチでき、全員が答えられたらゴール!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | なぞなぞ問題カード(1人1問)、小さなホワイトボードなど |
| 所要時間 | 15〜20分 |
| ねらい | 発想の転換、算数語彙への親しみ、仲間と支え合う協力性 |
例:
-
「『足しても引いても変わらない数』ってなーんだ?」(答え:0)
-
「2つで1つ、分けられないお菓子は?」(答え:クッキー)
教師ワンポイントアドバイス:
笑いが生まれる「ダジャレ系なぞなぞ」や「ことば遊び系」も混ぜると、緊張がとれてクラスの雰囲気が一気に和らぎます!
⑦ チームで挑戦!パズル図形チャレンジ
ゲーム内容
同じ図形を別の形に分けたり、組み合わせたりして「条件通りの図形」を作るチャレンジ。
正解の形は1つとは限らず、試行錯誤と発表の工夫が盛り上がるゲームです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | パズル図形プリント、はさみ、のり、A4用紙 |
| 所要時間 | 20〜25分 |
| ねらい | 図形の構成、空間認識、協力して意見をまとめる力 |
例題:
-
「この三角形を2つに切って、長方形を作ってください」
-
「この4枚のピースを正方形にしてください」
教師ワンポイントアドバイス:
途中で「他の班のやり方を1つだけ見学OK」などのルールを入れると、他者の考えを取り入れる良い機会に!発表タイムで工夫点を話すことで図形センスもUPします。
⑧ 魔法の三角形パズル

三つの数字が入る三角形の中に、法則を見つけて当てはめていくパズルです。思考の柔軟性や、筋道立てて考える力を育てます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 準備物 | プリント(図形問題)またはホワイトボードに図を提示 |
| 所要時間 | 10〜15分 |
| ねらい | 数字の関係性を論理的に考える力を育てる |
| 教師アドバイス | 「すぐに答えを言わず、ヒントで思考を誘導すると、考える力が育ちます」 |
活動例:
まとめ|算数は「考えるって楽しい」と感じることから
授業開きにおいて、ただ「算数の説明をする」のではなく、
「算数ってちょっと楽しいかも」「もっと考えてみたい!」という気持ちを引き出すことは、
その後の授業の雰囲気を左右するとても大切なポイントです。
小5・小6の子どもたちは、思考がぐんと深まり、論理性とひらめきの両方を楽しめる年代。
だからこそ、こうした「頭を使って遊ぶ」導入がよく刺さります。
今回ご紹介した7つのネタは、どれも「準備が簡単・導入しやすい」ものばかり。
もちろん、授業の本題につなげる「導入としての位置づけ」だけでなく、
週のはじめの“算数ブレイクタイム”としても、繰り返し使えますよ!
「うちのクラスに合いそう!」「これ、アレンジして使えそう!」というものがあれば、
ぜひ実践してみてくださいね。
✨関連記事はこちら⬇️
