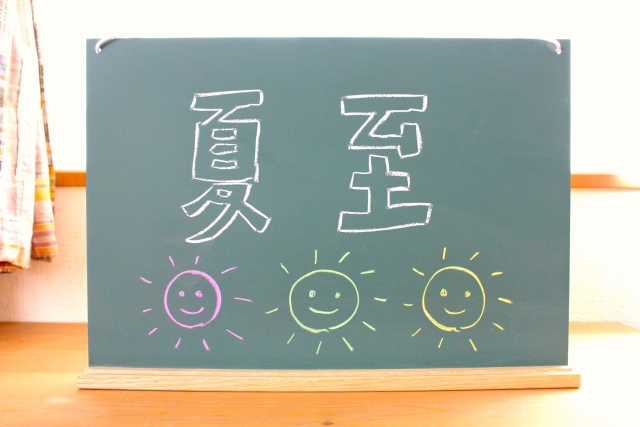
こんにちは。晴田そわかです。
今回の記事では《夏至とは?小学生と一緒に学べる雑学!意味・由来・風習まで解説》について紹介させて頂きます。
- ① 2025年6月21日は夏至!
- ② 夏至とは?やさしく解説
- ③ 夏至の意味と由来
- ④ 夏至にまつわる雑学5選
- ⑤ 日本の夏至の風習
- ⑥ 世界の夏至イベント
- ⑦ 夏至をテーマにした自由研究アイデア
- ⑧ まとめ:夏至を知ると季節の見方が変わる
① 2025年6月21日は夏至!
「夏至(げし)」という言葉、ニュースや天気予報などで一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?でも、「それって何の日?」と聞かれると、意外と説明できない人も多いかもしれません。
じつは夏至は、私たちの生活や自然のしくみに深く関わる、大切な節目の日です。特に小学生の自由研究や、親子の会話のネタとしてもぴったり。この記事では、小学生にもわかりやすく、そして大人にとっても学びのある「夏至」について、意味・由来・雑学・日本や世界の風習までたっぷりと解説します。
自然のリズムを知ることで、季節の感じ方がぐっと深まります。さあ、一緒に「夏至」の不思議な世界をのぞいてみましょう!
✨関連記事はこちら👇
② 夏至とは?やさしく解説

夏至とは、1年の中で「昼の時間」が最も長くなる日のことです。つまり、太陽が空に出ている時間が一番長く、逆に夜はとても短くなります。
地球は、太陽のまわりを1年かけてまわる(公転する)と同時に、自転(自分で回る)もしています。しかも、地球の軸は少し傾いているため、太陽の高さやあたる角度が、季節によって変わるのです。その結果、夏至の日には太陽が一年で一番高い場所に昇り、昼の時間が長くなるというわけです。
2025年の夏至はいつ?
2025年の夏至は、**6月21日(土)**です。実は夏至の日付は年によって少し変わることがあり、だいたい毎年6月20日~22日の間になります。これは地球の公転周期がぴったり365日ではなく、約365.24日であること、うるう年などが関係しています。
③ 夏至の意味と由来

「夏至」という言葉は、「夏(なつ)」と「至(いたる)」という漢字でできています。直訳すれば「夏に至る=夏がやってくるころ」という意味ですね。つまり、夏の本番が始まる目安として、昔から使われていた言葉です。
二十四節気と夏至の関係
夏至は、古代中国で作られた「二十四節気(にじゅうしせっき)」という暦(こよみ)の一つです。これは太陽の動きをもとに、1年を24の季節に分けたもので、日本の農業や暮らしの知恵にも深く関わっています。
「春分」「秋分」「冬至」などもこの二十四節気に含まれていて、「夏至」はその中の第10番目にあたります。昔の人たちは、夏至を田植えや稲作の目安として、非常に大切にしていました。
④ 夏至にまつわる雑学5選

ここからは、親子で話したくなるような「夏至の雑学」を紹介します。ちょっとした豆知識が、子どもたちの「なぜ?」「どうして?」という探究心をくすぐるかもしれませんよ。
1. 実は夏至が一番暑い日じゃない!
「昼の時間が長い=一番暑い日」と思われがちですが、実は一番暑くなるのは7月下旬から8月初旬ごろです。これは、「地面や空気が太陽の熱をためるのに時間がかかる」ため。つまり、太陽からのエネルギーがたくさん届く夏至のあと、それが蓄積されて気温のピークを迎えるのです。
この現象は「季節の時差」とも言われ、春も秋も同じように起こっています。
2. 夏至の太陽は真上に近くなる!?
夏至の日、太陽は空の高いところに昇ります。特に日本の関東地方では、太陽が真南からほぼ真上に近い位置を通過します。そのため、正午の影が一年で最も短くなり、まるで真下に落ちるような影になります。
この現象を観察するのは、小学生の理科の授業や自由研究にもぴったりです。
3. 日の出と日の入りの時間がズレる不思議
夏至の日は「昼が一番長い日」ですが、実は一番早く日の出を迎える日でも、一番遅く日没する日でもないのです。
たとえば、日の出は夏至の数日前に最も早くなり、日の入りは夏至の数日後に最も遅くなります。これは、地球の軌道や自転のズレによって起こる「均時差(きんじさ)」と呼ばれる現象です。少し難しい仕組みですが、「昼の長さ」と「日の出・日の入り」は必ずしも同じタイミングでピークを迎えるわけではないのです。
4. 北海道と沖縄では昼の長さがこんなに違う
夏至の日、日本の地域によっても「昼の長さ」が異なります。
-
**北海道(札幌)**では、昼の長さは約15時間22分
-
**沖縄(那覇)**では、昼の長さは約13時間54分
その差はなんと約1時間半以上もあります。これは、地球が丸いこと、そして北に行くほど太陽が長く出ているためです。日本の中でも場所によってこんなに差があるなんて、驚きですね。
5. 夏至の日にしか見られない自然現象も?
世界には、夏至の日にしか見られない現象もあります。
たとえば、北極圏の国々では**「白夜(びゃくや)」**と呼ばれる現象が起き、夜になっても太陽が沈まず、一日中明るいままになる地域があります。スウェーデンやフィンランド、ノルウェーなどが有名ですね。
日本では白夜までは起きませんが、「夜になってもなかなか暗くならない日」として夏至を実感できます。
⑤ 日本の夏至の風習

「夏至」と聞いて、すぐに何か特別な行事や食べ物を思い浮かべる人は少ないかもしれません。実際、冬至にはカボチャやゆず湯などのはっきりした風習がある一方で、夏至は少し地味な印象を持たれがちです。
しかし、日本各地には夏至にまつわる風習や食べ物がしっかりと伝わっている地域もあります。
● 関西地方では「タコ」を食べる習慣
大阪をはじめとした関西の一部地域では、夏至の日にタコを食べる風習があります。これは、「稲の根がタコの足のようにしっかりと地中に張るように」という農家の願いが由来です。
実際に、夏至の頃はちょうど田植えが終わり、稲が根を張り始める時期にあたるため、「根が張る=豊作祈願」の意味を込めてタコが選ばれたのです。
● 三重県・愛知県では「イチジク田楽」
愛知県や三重県の一部では、夏至のころに「イチジク田楽」というユニークな料理が登場します。イチジクを半分に切り、中に甘い味噌をかけて焼いたものです。
この料理も、暑さに負けないよう体を元気にするための知恵として伝えられてきました。
● 夏越の祓とのつながり
また、6月の終わりごろに行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」という神事とも関係があります。これは、半年分のけがれを祓い、残りの半年を健康に過ごすための儀式で、神社では「茅の輪(ちのわ)」と呼ばれる大きな輪をくぐる行事が行われます。
夏至から1週間ほどあとに行われることが多いので、夏の節目としてこの時期は特別視されていたことがわかります。
⑥ 世界の夏至イベント

夏至は日本だけでなく、世界中で「特別な日」として親しまれています。地域や宗教、文化によって、その祝い方や考え方もさまざまです。
● 北欧の「夏至祭(ミッドサマー)」
スウェーデンやフィンランド、ノルウェーなどの北欧諸国では、**「ミッドサマー(夏至祭)」**が盛大に祝われます。
この日は自然と太陽に感謝を込めて、野原で花の冠をかぶったり、伝統音楽に合わせて踊ったりと、日本の夏祭りに近い雰囲気があります。とくにスウェーデンでは国民的な祝日として、家族や友人と郊外で過ごす習慣が根づいています。
● イギリス・ストーンヘンジでの儀式
イングランド南部にある古代遺跡「ストーンヘンジ」では、夏至の朝、太陽が特定の石の隙間から昇るという神秘的な現象が見られます。
そのため、毎年6月21日前後には数千人もの人が世界中から集まり、太陽の動きと自然の神秘を感じるための儀式や瞑想、祝祭が行われます。
● アメリカやカナダのサマーイベント
北米では特に宗教色は少ないものの、キャンプや音楽フェスティバル、自然観察ツアーなどが多く開催され、夏至を「自然とつながる日」として楽しむ傾向があります。
⑦ 夏至をテーマにした自由研究アイデア

夏至は「自然」「時間」「文化」が関係するテーマなので、自由研究にもおすすめです。ここでは、小学生でも取り組みやすい自由研究のアイデアを3つご紹介します。
アイデア①:自分の住む地域の「昼の長さ」を調べよう
天気アプリや国立天文台のサイトで、夏至の日の日の出・日の入り時刻を調べ、昼の長さを計算してみましょう。さらに、冬至と比べてグラフにすれば、変化が一目瞭然です。
工夫次第で社会・理科・算数の要素を盛り込めます。
アイデア②:影の長さを観察して記録しよう
夏至の日の正午に、地面に立って自分の影の長さを測りましょう。1年のうちで最も短い影になるはずです。別の季節にも同じ方法で測ると、太陽の高さの変化を観察できます。
紙にスケッチして記録すれば、理科の自由研究にぴったり!
アイデア③:日本と世界の夏至の風習を調べよう
インターネットや図書館の本を使って、日本や世界の「夏至の風習」を調べてまとめましょう。国ごとの行事を地図に表したり、写真を貼ったりして発表用ポスターを作ると、見栄えも◎です。
⑧ まとめ:夏至を知ると季節の見方が変わる
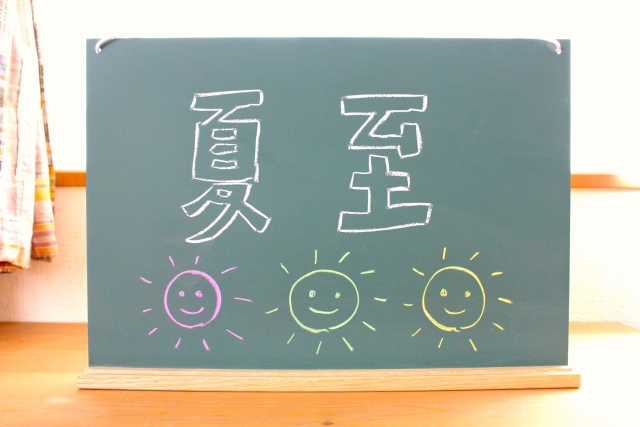
「夏至」は、ただ昼が長くなる日というだけでなく、自然と私たちの暮らしをつなぐ大切な節目です。
太陽の高さや影の長さ、夜の短さなど、ちょっとした自然の変化に目を向けることで、毎日の生活がより豊かになります。そして、夏至にまつわる風習や雑学は、子どもにとっても大人にとっても、発見と学びのきっかけになります。
日々の暮らしに追われる中でも、季節の変化に目を向け、「今日は夏至なんだ」と感じられる心のゆとりを持つこと。それが、自然とともに暮らす第一歩かもしれません。
親子で一緒に、空を見上げてみませんか?
✨関連記事はこちら👇