
こんにちは。晴田そわかです。
今回の記事では《小学生にわかりやすい!夏至とは?意味や由来を豆知識で解説》について紹介させて頂きます。
- ① もうすぐ夏至(6月21日/2025年)
- ② 夏至とは?かんたんに説明しよう
- ③ 夏至の由来や歴史
- ④ 夏至にまつわる豆知識(親子で楽しめる話題)
- ⑤ 夏至に関する小学生向けクイズ(自由研究のヒントにも)
- ⑥ 夏至をテーマにした自由研究のアイデア
- ⑦ まとめ:夏至を知ると、季節がもっと楽しくなる!
① もうすぐ夏至(6月21日/2025年)
梅雨の合間に、ふと空を見上げると、いつの間にか陽が長くなってきたなあ……と感じることはありませんか? 6月になると、ニュースなどで「今日は夏至です」と聞くこともあります。でも、「夏至」って実際にはどんな日なのか、説明できる大人は意外と少ないかもしれません。
この記事では、小学生でも楽しく読めるように、夏至の意味やその由来、そして思わず話したくなるような豆知識を紹介します。自由研究のヒントにもなる内容ですので、親子で一緒に読んで、季節を感じる時間を楽しんでみてくださいね。
✨関連記事はこちら👇
② 夏至とは?かんたんに説明しよう
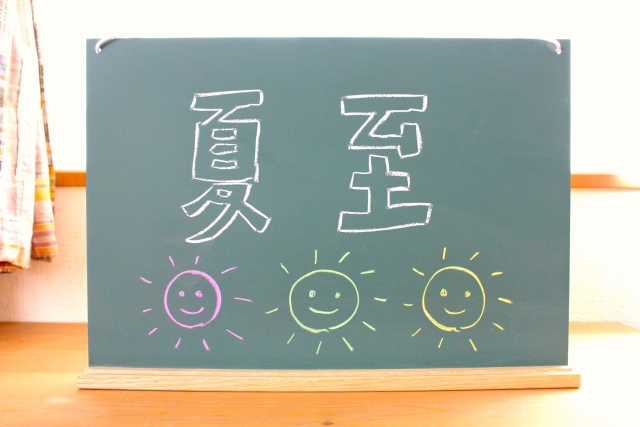
まずは「夏至(げし)」という言葉の意味から見ていきましょう。
夏至とは、1年の中で「昼の時間」が最も長くなる日のことです。これはつまり、太陽が空に出ている時間が一番長くなる日、ということ。逆にいうと、夜が一番短くなる日でもあります。
たとえば、普段は夕方6時ごろに暗くなるところが、夏至の頃には7時近くまで空が明るかったりします。「なんだか今日はなかなか暗くならないな」と感じたら、それは夏至が近い証かもしれません。
2025年の夏至はいつ?
2025年の夏至は「6月21日(土)」です。ただし、これは年によって少し前後します。たとえば、ある年は6月22日だったり、別の年は6月20日だったり。これは地球の公転周期やうるう年などが関係しています。
昼が長くなる理由って?
地球は自転しながら、太陽のまわりをぐるぐると1年かけてまわっています。この地球の公転軌道や傾きの関係で、ある日を境に太陽の高さが少しずつ変化します。そして、太陽が空の中で最も高い位置を通る日が「夏至」なのです。
太陽が高くのぼれば、それだけ地平線から出て地平線に沈むまでの時間も長くなります。だから、昼の時間が長くなるのですね。
③ 夏至の由来や歴史

次は、夏至という言葉の由来や、どうして昔から大切にされてきたのかを見ていきましょう。
「夏至」という漢字の意味
「夏至」は、「夏(なつ)」と「至(いたる)」という漢字でできています。これは、夏に至る=本格的な夏がやってくるころという意味。つまり、「夏の入り口」を知らせる言葉でもあるのです。
この言葉は、昔の中国から伝わった「二十四節気(にじゅうしせっき)」のひとつに含まれています。
二十四節気ってなに?
二十四節気とは、太陽の動きをもとに1年を24の時期に分けたものです。現代のカレンダーができるよりもずっと前、農業が生活の中心だった時代、人々は季節の移り変わりをとても大切にしていました。
そのため、太陽の位置をもとに「種をまく時期」「田んぼに水を引く時期」「収穫する時期」などを決めるための目安として、二十四節気が使われていたのです。
たとえば「春分」「秋分」「冬至」などもその仲間。夏至もその中のひとつで、「夏に入る時期」「本格的な暑さの始まり」を知らせる日として、古くから知られていたのです。
④ 夏至にまつわる豆知識(親子で楽しめる話題)

夏至という言葉には「天文学的な説明」だけでなく、日常の中にちょっとした「発見」や「驚き」が隠れています。ここでは、親子で会話のきっかけになるような、夏至に関する面白い豆知識を紹介します。
実は夏至は「一番暑い日」じゃない?
「昼の長さが一番長い日」と聞くと、つい「一番暑い日なんじゃないの?」と思いがち。でも、実は一番暑くなるのは7月後半から8月の初めごろなんです。これは「季節のズレ」や「地面の熱のたまり方」に関係があります。
たとえば、お風呂に水を入れて火をかけたとき、火を止めてもすぐには冷めませんよね。それと同じように、地面や空気も太陽の熱をじわじわためてから、ようやく気温が上がってくるのです。
地域によって違う!? 夏至の食べ物
「冬至にカボチャを食べる」という話はよく知られていますが、夏至にも地域によってさまざまな食べ物の習慣があります。
-
**関西地方(大阪など)**では、「タコ」を食べる風習があります。これは、稲がタコの足のようにしっかり根を張るように、という願いを込めたものだとか。
-
愛知県の一部では、「イチジク田楽」という料理を食べる地域も。甘いイチジクと味噌の組み合わせが夏の味覚として楽しまれています。
-
一部の農村では、「うどん」を食べて力をつける風習もあります。
こうした習慣は、どれも「農業」や「自然とのつながり」を感じる行事ですね。
なぜ「夜が短い」のに気づきにくい?
夏至は夜が一番短い日でもありますが、実際に体感として「今日は夜が短いな!」と思う人は少ないかもしれません。それには理由があります。
実は、夏至の前後には、日の出の時間と日の入りの時間が同時に変わっているんです。たとえば、日の入りはだんだん遅くなるのに、日の出はあまり早くなっていなかったり。つまり、「朝早く起きない人」には、夜の明るさだけが目立って見えるというわけです。
こういった“気づかないズレ”が、夏至の面白いところですね。
世界にもある!夏至を祝う行事
日本だけでなく、世界中でも「夏至」は特別な日として祝われています。
-
スウェーデンやフィンランドなどの北欧では、「夏至祭(Midsummer Festival)」が行われます。草花で作った冠をかぶったり、野外でダンスや音楽を楽しんだりと、まさに夏の訪れを全身で祝うお祭りです。
-
イギリスのストーンヘンジでは、太陽の位置に合わせて巨大な石の間から朝日が差し込むという神秘的な現象を見に、多くの人が集まります。
自然や太陽と向き合う文化は、国や地域を超えて大切にされているのですね。
⑤ 夏至に関する小学生向けクイズ(自由研究のヒントにも)

ここで、夏至にまつわるクイズに挑戦してみましょう! 親子で一緒に考えたり、自由研究の導入にもぴったりです。
Q1:夏至の日は、昼が長い?夜が長い?
A. 昼が長い!
👉 地球の傾きと太陽の高さによって、1年で最も昼の時間が長くなる日です。
Q2:夏至と反対に、昼が一番短い日はなんという?
A. 冬至(とうじ)
👉 冬至は12月ごろにあり、夏至とは反対に「夜が一番長い日」です。
Q3:夏至の頃に関西地方でよく食べられるものは?
A. タコ!
👉 「タコの足のように稲がしっかり根を張るように」という願いが込められています。
👉 2025年は6月21日です。毎年ちょっとだけ前後します。
Q5:夏至の時期に日本よりも太陽が沈まない国は?
A. 北欧(ほくおう)
👉 スウェーデンなどの国では、夏の間ずっと太陽が沈まない「白夜(びゃくや)」の現象が見られます!
⑥ 夏至をテーマにした自由研究のアイデア

夏至は、太陽や季節の変化に興味を持つきっかけになります。ここでは、小学生が取り組みやすく、楽しく学べる夏至に関する自由研究アイデアを3つ紹介します。
アイデア①:自分の住む町の日の出・日の入りを調べてみよう
まずはインターネットや天気アプリを使って、自分が住んでいる地域の「日の出」と「日の入り」の時刻を調べてみましょう。夏至の前後1週間や、冬至と比較してグラフを作ると、昼の長さがどう変わるのかがよくわかります。
ポイント:
-
グラフにすると視覚的にわかりやすい
-
他の地域(東京と札幌、大阪と那覇など)とも比べてみよう!
アイデア②:世界と日本の「夏至の食べ物・行事」を調べよう
地域によって、夏至の風習はずいぶん違います。たとえば、日本ではタコやイチジク、スイカなどを食べる地域がありますが、北欧では「夏至祭」で花冠をかぶるなど、まったく違う文化も。
国や地域ごとにまとめて、地図や写真を使って発表資料にするのもおすすめです。
ポイント:
-
図書館やインターネットを活用して調べる力を育てよう
-
文化の違いを知ることで国際理解にもつながる
アイデア③:夏至の日の「影」を観察しよう
夏至の日、太陽が一番高くのぼる時間(お昼の12時ごろ)に、自分の影を観察してみましょう。紙に足の位置を決めて、影の長さを測ったり、形をスケッチするのも面白いですね。
さらに、別の日(たとえば秋分や冬至)にも同じ場所・時間で影を比べると、太陽の高さの違いがわかります。
ポイント:
-
定点観測にチャレンジ!
-
理科や天文学への興味にもつながるテーマです
⑦ まとめ:夏至を知ると、季節がもっと楽しくなる!

「夏至」という言葉には、単に“昼が長い日”という意味以上に、自然と人との深いつながりが詰まっています。
地球がどんなふうに太陽のまわりをまわっているのか。なぜ昼が長くなるのか。昔の人たちはそれをどう暮らしの中で感じ、行事や食べ物に結びつけてきたのか……。こうしたテーマは、大人でも改めて学びたくなるような奥深さがあります。
また、自由研究として夏至をテーマにすることで、天文学、文化、社会科、理科、国語などさまざまな学びの要素を自然と身につけることができます。
太陽の動きに少しだけ目を向けてみるだけで、季節がもっと身近に、もっと楽しく感じられるようになります。ぜひこの機会に、親子で「夏至ってなんだろう?」と会話してみてくださいね。
✨関連記事はこちら👇