 こんにちは。晴田そわかです。
こんにちは。晴田そわかです。
今回の記事では《【保存版】国語の授業開きアイデア|小学生・低学年クラスで使えるネタ集》について紹介させて頂きます。
- 1. 授業開き、何しよう?と悩んでいませんか?
- 2. 国語の授業開きで育てたい「3つの力」
- 3. 授業開きにぴったり!低学年向けネタ10選
- 活動①:「ことばであいさつ」ビンゴ
- 活動②:じぶんの名前であいうえお作文
- 活動③:教科書の“絵”だけ見てお話づくり
- 活動④:先生・友達にインタビュー
- 活動⑤:「すきな言葉」をさがそう
- 活動⑥:「つたえあいメッセージカード」
- 活動⑦:「国語の道具箱クイズ」
- 活動⑧:「きいて!みんなの“はじめて”ばなし」
- 活動⑨:「ことばの福笑い」
- 活動⑩:「ことばのたからばこ」
- 4. アクティビティ活用のポイント
- 5. まとめ|国語の授業開きが楽しいと、1年がうまくいく!
- 国語の授業開きを、ことばと出会うワクワクの時間に
1. 授業開き、何しよう?と悩んでいませんか?
新年度。新しい教室、新しい仲間、新しい教科書。子どもたちにとっては、ドキドキとワクワクが入り混じるスタートです。
でも、教師にとってもこの「はじめの一歩」はとても大切な時間。特に低学年の子どもたちにとって、国語の授業開きは「学校の授業ってこんな感じなんだ」と思ってもらう大事な第一印象になります。
とはいえ、いきなり教科書を開いて音読…というのはちょっと早すぎるかもしれません。
「ことばっておもしろいな」「話すのって楽しいな」と、国語の時間を好きになってもらうためには、少し遊び心のある活動や、交流を深めるアイデアが役に立ちます。
この記事では、低学年クラスの国語授業開きにぴったりのネタをたっぷりご紹介します。
すべて、実際の教室で使いやすく、準備もかんたんなものばかり。授業づくりのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
2. 国語の授業開きで育てたい「3つの力」

授業開きのアイデアをご紹介する前に、まずは「そもそも国語の授業開きって、何のためにやるの?」という視点を確認しておきましょう。単なるウォーミングアップではなく、しっかりと意味のある活動にしていくことが大切です。
① ことばに親しむ力
国語の基本は「ことば」。まずは、ことばを使うって楽しい、伝えるって面白い、というポジティブな体験をしてもらうことが最優先です。
② 友達とのつながり
国語の授業では、話し合いや読み聞かせ、ペア活動など、人と関わる学びがたくさんあります。授業開きの段階で、友達と安心してやりとりできる雰囲気をつくっておくと、今後の授業がとてもスムーズになります。
③ 自己表現への意欲
低学年でも、自分の気持ちや考えを「ことば」にする経験をたくさん積むことが大切です。授業開きでは、小さな成功体験を通して、「話してみよう」「書いてみよう」という気持ちを引き出すことができます。
3. 授業開きにぴったり!低学年向けネタ10選
ここからは、実際に教室で使えるアイデアを10個紹介します。どれも低学年の子どもたちが楽しく取り組める内容ばかり。1日で全部やらなくても、数日に分けて「授業開き週間」にして取り入れるのもおすすめです。
活動①:「ことばであいさつ」ビンゴ
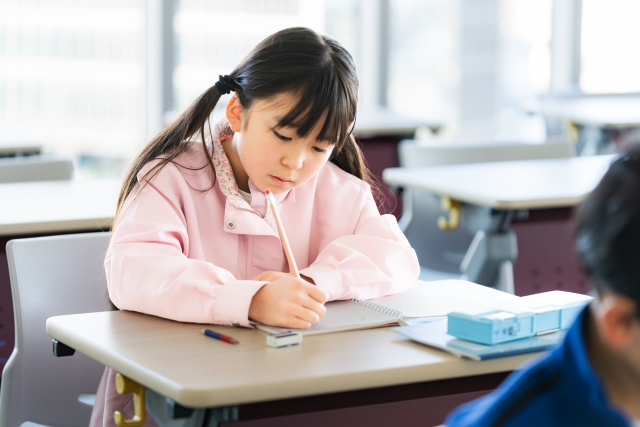
最初にぴったりなのが、この“あいさつビンゴ”。「おはよう」「ありがとう」「こんにちは」「またね」など、いろいろな言葉のビンゴカードを用意します。
子どもたちはカードを持って、友達に声をかけながらビンゴを進めていきます。ただし、条件は「その言葉にぴったりの場面であいさつすること」。
たとえば、「ありがとう」のマスを開けたいときは、何かを手伝ってくれた子に「ありがとう」と伝える…といった感じです。
活動を通して、ことばの持つあたたかさや意味を自然に感じ取ることができ、クラスの雰囲気づくりにもぴったりです。
ねらい:
-
基本的なあいさつの言葉を知り、場に応じて使い分ける力を育てる
-
クラスメイトとの交流を通して、教室に安心感をもつ
方法:
-
「おはよう」「ありがとう」「ごめんね」「こんにちは」「またね」などのあいさつをビンゴカードに配置(9マス〜16マス程度)。
-
子どもたちは友達に声をかけながら、場面に合ったあいさつを交わし、マスに〇をつける。
-
ビンゴができたら全体で発表。「誰にどんなあいさつをしたか」を共有。
※最初は「ありがとう」「こんにちは」など使いやすい言葉を選ぶのがポイントです。
活動②:じぶんの名前であいうえお作文
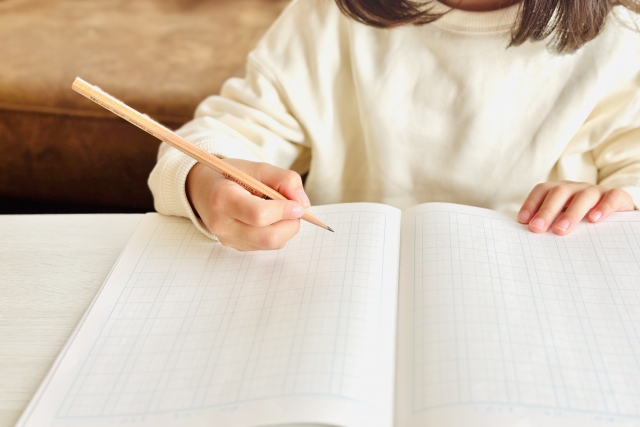
国語といえば“ことば遊び”! その入門としてぴったりなのが、「あいうえお作文」。
自分の名前を使って、一文字ずつことばを考えていきます。
たとえば、「さき」ちゃんの場合:
-
さ:さくらがさくころ
-
き:きょうから1ねんせい!
できあがった作文を発表したり、廊下に掲示したりすることで、自分を表現する楽しさとことばを選ぶ面白さを感じることができます。
ねらい:
-
名前の文字を使って言葉をつくることで、語彙力や発想力を育てる
-
自己紹介の一環として、自分を表現することに親しみをもつ
方法:
-
名前の文字を縦に並べたワークシートを用意(「ひ」「ろ」「し」など)。
-
それぞれの文字から始まる文を考えて記入。1文でなくても、単語だけでもOK。
-
書けた子は前に出て発表。簡単な絵を添えて掲示すると、より教室が明るくなる。
例)「さ さくらがさくころ き きょうから1ねんせい!」
活動③:教科書の“絵”だけ見てお話づくり

教科書を開くのはまだ早い…でも、中をのぞいてみたくなるようなワクワクも大切。
そこでおすすめなのが、「絵だけ見る活動」です。
1年生の教科書にはたくさんのイラストが載っています。その中から1枚選び、「この絵からどんなお話が始まりそう?」と問いかけてみましょう。
子どもたちは想像をふくらませ、「きっとここでケンカしてる!」「この子は困ってるのかも」など、自由に発言してくれます。
こうした活動は、想像する力や話す力を引き出すきっかけにもなりますし、「国語=正解を当てる教科じゃない」という安心感にもつながります。
ねらい:
-
絵を手がかりにした想像活動を通して、話す・聞く力を育てる
-
教科書への興味を引き出す
方法:
-
教科書から、絵が大きく描かれているページを数枚選ぶ(文字を隠して見せる)。
-
1枚の絵をみんなで見て、「この子は何をしているのかな?」「どんな気持ち?」など問いかける。
-
子どもたちが自由に話す。話の続きを考えるのもOK。
※最後に、「このお話、教科書であとで読むんだよ」と伝えると、興味がぐっと高まります。
活動④:先生・友達にインタビュー

「話す」「聞く」を両方楽しめるアクティビティとしておすすめなのが、インタビューごっこ。
簡単な質問(すきな食べ物・好きなあそび・よく行く場所など)をいくつか用意して、先生や友達にインタビューをします。
答えてもらった内容は、ノートに書いてもいいし、イラストでまとめてもOK。
お互いのことを知ることで信頼関係も深まり、「もっと話したい」「もっと聞きたい」という気持ちが育ちます。
ねらい:
-
相手の話をよく聞き、自分の言葉でまとめる練習
-
友達との関係づくり・コミュニケーションの土台づくり
方法:
-
あらかじめ質問を数個準備(例:「すきなたべもの」「すきなあそび」「すきなどうぶつ」など)
-
ペアやグループになって、お互いにインタビュー。聞いたことを紙にまとめる。
-
書いた内容を使って「○○さんは〜がすきなんだって!」と紹介し合う。
※1年生の場合は絵やシールを使った簡単なメモでも十分です。
活動⑤:「すきな言葉」をさがそう

「すきな言葉って、ある?」という問いかけからスタートするこの活動は、ことばに親しむ入り口としてとても効果的です。
絵本のセリフ、教室で聞いた言葉、自分でつくった言葉でもOK。
「ふわふわ」「にこにこ」「どっきり」など、言葉そのものが面白かったり、言ってみたくなるような音がしたり…。
発表してもらいながら「どうしてそれが好きなの?」と聞いてみると、言葉の背景にある気持ちや経験を自然と語ってくれます。
ねらい:
-
響きや意味のおもしろさから、ことばへの興味を高める
-
言葉を通して、自分の気持ちや経験を表現する
方法:
-
「すきな言葉ってある?」と問いかけ、黒板に書いていく。
-
「なぜそれが好きなの?」と質問し、子どもたちの思いや背景を聞き合う。
-
自分のすきな言葉を絵や文でカードに書き、教室に掲示する。
※「ふわふわ」「ぴかぴか」などのオノマトペや、聞いたことのある名言もOK。
活動⑥:「つたえあいメッセージカード」

ねらい
-
伝える力と聞く力の導入
-
ことばが持つ“あたたかさ”を体験する
方法
-
ひとり1枚、小さなカードを配ります(名刺サイズがおすすめ)。
-
隣の席の友達に伝えたい「ポジティブなひとこと」を書きましょう。
たとえば……
「よろしくね」
「かばんのキーホルダー、かわいいね」
「えんぴつの使い方がじょうずだね」 など。 -
イラストを添えることで、ことば+気持ちの表現になります。
-
書いたカードは、そっと相手に渡します。
-
全員が渡し終えたら、感じたことをクラス全体で共有しましょう。
「うれしかった」「ドキドキした」など、受け取った側の気持ちを聞くことで、“ことばが人の心を動かす”という感覚が生まれます。
📌 ポイント
・ネガティブな言葉は禁止。「うれしくなる言葉を使うよ」とあらかじめ伝えておくと安心です。
・子どもたちの作品は掲示してもOK! クラス全体があたたかい雰囲気になります。
活動⑦:「国語の道具箱クイズ」

ねらい
-
国語の学習に使う道具を知る
-
国語の学習内容が「書く・読む」だけでないと知る
方法
-
教室の前の机に、以下のような道具をいくつか用意して並べておきます。
・国語の教科書
・ノート
・えんぴつ
・下じき
・赤青えんぴつ
・ホワイトボード
・タイマー
・折り紙(おまけ的に) など -
子どもたちにクイズ形式で問いかけます。
「この中で、国語のじゅぎょうで使うものはどれかな?」
「これは何をするときに使うのかな?」 -
道具を手に取りながら、一つずつ簡単に用途を紹介。
・ノート→お話を書いたり、ことばをまとめたり
・タイマー→話す時間をはかるよ
・ホワイトボード→グループで考えを書くときに使えるね -
「折り紙は使う?」といったユーモアのある問いも入れると、場が和みます。
📌 ポイント
・「話す」「聞く」「考える」など、国語の広がりを実感できるように促します。
・“この道具をつかって、どんなことをしてみたい?”と聞いてみると、子どもたちの創造力がふくらみます。
活動⑧:「きいて!みんなの“はじめて”ばなし」

ねらい
-
話すこと、聞くことの楽しさを知る
-
友達との共感・発見を通して、クラスの仲を深める
方法
-
テーマは「はじめて」。今日の学校生活の中で、“はじめて”を探してもらいます。
・今日、はじめて持ってきた文房具
・朝、はじめて○○をしてみた
・はじめての国語のじゅぎょうで思ったこと -
1人ずつ、1〜2文で「はじめてばなし」を発表します。
例:「きょうはじめて、ランドセルにおべんとうをいれたよ!」
「はじめてのおともだちができました!」 -
聞いている子たちは、「へぇ〜!」「すごい!」と思ったら、拍手や「おぉ〜」というリアクションをしてOK。
-
話すことがちょっぴり苦手な子も、みんなの温かいリアクションで安心して話せる雰囲気をつくりましょう。
📌 ポイント
・「発表がうまい」よりも、「自分のことをことばにするって楽しい」と感じてもらうことが大事。
・“聞いてくれてありがとう”の気持ちも忘れずに。最後に「お話を聞いてくれてありがとう」と一斉に言うと、良い締めになります。
活動⑨:「ことばの福笑い」

ねらい
-
擬音語・擬態語に親しみ、語彙を楽しく広げる
-
発想力をことばと絵に結びつける体験
方法
-
あらかじめ「ことばカード」を用意します。カードには擬音語・擬態語がひとつずつ書かれています。
(例:ふわふわ/ぴかぴか/ニコニコ/ガミガミ/ドキドキ/キラキラ) -
子どもたちには1人1枚カードを引いてもらい、そこに書かれたことばにぴったりな「顔」を紙に描いてもらいます。
・「ふわふわ」なら、やさしい目とにっこりした口の顔
・「ガミガミ」なら、怒ったようなまゆげと口の顔 -
描いた顔を友達と見せ合い、「どんな気持ちをえがいたの?」とシェアタイム。
「これ、ふわふわのおふとんを思い出してかいたよ」
「ガミガミは、おこられたときのきもちかな〜」など、ことばへのイメージをふくらませていきます。 -
みんなの顔を黒板や掲示板に並べて、「ことばの気もちギャラリー」にしても楽しいです。
📌 ポイント
・同じことばでも、顔の描き方は十人十色。違いを認め合いながら、ことばの奥深さに気づくきっかけになります。
・発表が苦手な子には、担任が「これは○○なときの顔?」と質問形式でサポートすると安心です。
活動⑩:「ことばのたからばこ」

ねらい
-
1年間の国語学習へのワクワク感を育てる
-
子どもたちの「ことばアンテナ」を立てる
方法
-
授業開きの日に「クラスのことばのたからばこ」を紹介します。
画用紙で作った箱でも、空き箱を飾ってもOK。ラベルに「ことばのたからばこ」と書いておきましょう。 -
先生がまずお手本として、2つほどことばを書いて入れます。
たとえば……
・「おはようって言われて、心がぽかぽかしたよ」→【おはよう】
・「本で見つけた“すいすい”ってことば、気に入ったよ」→【すいすい】 -
1年間を通して、子どもたちが見つけた「すてきなことば」「おもしろいことば」「言ってみたくなったことば」を紙に書いて、宝箱に入れていきます。
-
学期末や節目のタイミングで宝箱を開き、みんなでことばを振り返る時間をつくりましょう。
📌 ポイント
・導入では“ことばって、見つけると楽しいんだよ”というワクワクを伝えるのがカギ。
・活動のハードルは低く。書けたらラッキーくらいの気軽さで始めると、継続につながります。
・「おもしろことばコーナー」などに掲示しても盛り上がります。
4. アクティビティ活用のポイント

■「授業開き週間」という考え方で、じっくりスタート
新年度初日の国語の授業で、すべての活動を一気にやろうとすると、時間も心の余裕も足りなくなりがちです。
だからこそおすすめしたいのが、**「授業開き週間」**として数日かけて国語の導入を進めていくこと。
たとえば——
-
1日目:「教科書をひらく前のことば遊び」(活動①〜②)
-
2日目:「話す・聞くを楽しむ導入」(活動③〜④)
-
3日目:「書くことに親しむ・1年の見通し」(活動⑤〜⑦)
-
4日目以降:「ことばの感性を育てる&目標づくり」(活動⑧〜⑩)
このように、子どもたちの様子や学級の雰囲気を見ながら、ゆるやかに導入していくスタイルがおすすめです。
「今日は国語でこれやるんだ〜!」と楽しみに登校してくれるような数日間をつくることで、教科への期待感がふくらみます。
■ 子どもの反応を見ながらアレンジしよう
紹介したアクティビティは、どれもそのまま使っていただけますが、子どもたちの様子に応じたアレンジもとても大切です。
-
おしゃべりが苦手そうなら、書く活動から入ってみる
-
盛り上がりそうな学級なら、ことばあそびを中心に
-
自分の気持ちを出すのが難しそうなクラスなら、先生のお手本をしっかり見せてから
どの活動にも**「楽しくことばに出会える工夫」**が詰まっています。活動を途中で切り上げても大丈夫。無理にやりきるより、「またやってみたい!」の気持ちが残る方がずっと効果的です。
■ 「ねらい」を意識すると効果倍増!
授業開きでありがちなのが、「楽しかったけど、それで終わってしまう」こと。
もちろん楽しさは大切。でも、せっかくなら学習のねらいと結びつけることで、学びとしても印象に残る時間にしたいですよね。
そこで活躍するのが、**活動ごとの「ねらい」**です。
-
「伝える力を育てる」
-
「ことばの面白さを知る」
-
「語彙を広げる」
-
「考える力・聞く力を高める」
授業の最後に、「今日の活動で○○な力をつかったね」「こんなときに今日のことが役立つね」とふりかえるだけでも、学習へのつながりがぐっと深まります。
5. まとめ|国語の授業開きが楽しいと、1年がうまくいく!

国語は、日常に最も身近な教科。だからこそ、「国語の授業が好き」という気持ちが、学校生活全体の土台になることも少なくありません。
■ 楽しさと安心感が「好き」を育てる
「国語って、むずかしそう」
「読むの苦手だなあ」
そんな気持ちをもっている子どもでも、授業開きでことばの楽しさやぬくもりに触れられたら、教科への印象は大きく変わります。
活動を通して、「わたしもできた!」「ことばって、おもしろい!」という安心感と成功体験を積み重ねていくことが、長い1年間の学びを支える力になります。
■ 導入がうまくいけば、今後の授業もスムーズに
「このクラスの国語、楽しみ!」
そう思ってもらえる導入ができれば、その後の物語文・説明文の読解や、書く学習にも前向きに取り組めるようになります。
「ことばと向き合うってこういうことなんだな」
「先生は、わたしたちの気もちや考えをたいせつにしてくれるんだ」
そんな信頼関係も、授業開きの短い時間の中から芽生えていきます。
■ まずは先生が楽しむこと!
なにより大切なのは、先生自身が楽しんで授業をすることです。
どんなにすてきな活動でも、先生が「おもしろい!」と心から思っていないと、子どもには伝わりません。
逆に、先生がにこにこして活動を紹介していたら、子どもたちは自然と引きこまれます。
最初は緊張していたクラスにも、笑顔が広がっていくはずです。
国語の授業開きを、ことばと出会うワクワクの時間に
新しい学年の始まりは、子どもたちにとっても、先生にとっても特別な時間。
国語の授業開きを、ことばとの出会い・クラスの仲間との出会いを楽しく彩る時間にしてみませんか?
今回ご紹介したアイデアが、先生方の国語スタートの一助になればうれしいです。
少しの工夫と準備で、きっと子どもたちは「国語って好き!」と感じてくれるはずです。
✨関連記事はこちら🔽