 こんにちは。晴田そわかです。
こんにちは。晴田そわかです。
今回の記事では《小学生と学ぶ「穀雨」ってどんな季節?自然のリズムにふれる春の豆知識》について紹介させて頂きます。
- ① 小学生と一緒に、季節を感じてみよう
- ② 「穀雨」ってなに?基本の意味を知ろう
- ③ 「穀雨」と農業の深い関係
- ④ 穀雨のころ、自然はどうなってる?
- ⑤ 暦の知恵:なぜ「穀雨」みたいな名前があるの?
- ⑥ 小学生にもできる!穀雨のころの自然観察
- ⑦ 学校の授業や自由研究にもつながる!
- ⑧ まとめ:穀雨から自然と心をつなぐ時間へ
① 小学生と一緒に、季節を感じてみよう
「春」や「秋」など、日本には四季があります。ですが最近、「季節の移り変わりがよくわからなくなった」と感じている方も多いのではないでしょうか。特に都市部では、冷暖房や人工的な環境に囲まれて生活しているため、空気のにおい、草花の成長、虫の動きといった自然の小さな変化に気づきにくくなっています。
そんな今だからこそ、改めて「季節」を見つめ直してみませんか?
今回は、春の最後をしめくくる節目である「穀雨(こくう)」について、小学生でもわかるようにやさしく、そして大人にとっても学びのある視点でご紹介していきます。
この記事では、「穀雨」の意味やその由来、自然や農業との関係、そして実際に親子でできる自然観察のヒントまで、幅広くまとめています。普段の生活の中で、少しだけ目を向けるだけで、私たちの身の回りには豊かな季節のサインがあることに気づけるはずです。
✨関連記事はこちら⬇️
② 「穀雨」ってなに?基本の意味を知ろう
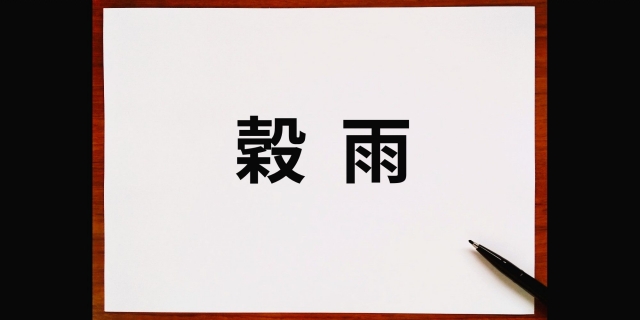
「穀雨」とは、二十四節気(にじゅうしせっき)のひとつです。毎年4月20日ごろに訪れ、暦のうえでは「春の最後の節気」とされています。
漢字で書くと「穀物の雨」。この言葉のとおり、稲や麦などの穀物を育てるのにちょうどよい、やさしい雨が降る季節を意味します。
二十四節気は、1年を24の季節に分けた古い暦(こよみ)です。日本だけでなく中国や韓国などでも使われており、太陽の動きを基準にしてつくられています。たとえば「立春」「夏至」「冬至」などは、聞き覚えのある方も多いでしょう。
穀雨は、その中でも「春の終わりを告げる」節気。
この時期の雨は、たんに「濡れるもの」「うっとうしいもの」ではなく、作物にとっては“恵み”そのもの。冬の寒さに耐えてきた土や植物が、ようやく息を吹き返し、生き生きと活動をはじめるタイミングでもあるのです。
③ 「穀雨」と農業の深い関係

穀雨の時期に注目すると、自然と「農業」の話にたどりつきます。
昔の人々は今のように気象予報や農薬、灌漑設備(かんがい=水を田畑に流す仕組み)が整っていなかったぶん、自然のリズムに合わせて暮らすしかありませんでした。
そのなかで、「この時期の雨は、作物にとって本当に大切だ」と気づいた人たちが、名前をつけて暦に取り入れたのが「穀雨」です。
この時期、農家では稲の苗代(なわしろ)作りがはじまり、麦はちょうど育ちざかり。どちらにとっても、春の終わりの適度な雨と気温は欠かせない要素です。
さらに、田んぼに水を引き入れる「代かき(しろかき)」の準備も進みはじめ、いわば**“田んぼの目覚まし時計”が鳴るころ**とも言えます。
日本の農業は自然と密接に結びついてきた歴史があります。私たちが口にするお米や野菜、その背景にある自然のリズムを意識することで、食べ物のありがたさにも改めて気づけるかもしれません。
④ 穀雨のころ、自然はどうなってる?

穀雨の頃になると、自然界にもさまざまな変化が現れます。春の陽気が本格的になり、冬の眠りから目覚めたように、生きものたちが一気に活動をはじめる時期です。
たとえば、田んぼに水が引き入れられ、鏡のように空を映す光景が見られるのもこの時期。カエルの声が聞こえてくると、「ああ、田植えが近いんだな」と感じる方もいるでしょう。都市部にお住まいの方は、水田を見る機会が少ないかもしれませんが、少し足を伸ばして郊外に出かけると、今もこうした風景に出会うことができます。
また、ツバメが日本に戻ってくるのも穀雨のころです。ツバメは春から夏にかけて日本で子育てをし、秋には東南アジア方面へと旅立っていきます。その姿を見かけたら、「あ、穀雨の時期なんだな」と自然のリズムを感じてみてください。
植物にも注目してみましょう。桜が散り、新緑の美しい若葉が目立つようになり、野原にはタンポポやナズナ、ツクシなどが顔を出します。雨のあとには、ぐんと伸びた草や、つやつやとした葉の色がより鮮やかに感じられ、「生きている」ことの力強さが伝わってきます。
穀雨の時期に降る雨は、しとしとと静かで、空気に湿り気がありながらも寒さを感じさせません。このやわらかく温かい雨こそが、自然の営みにとってのスイッチのような存在なのです。
⑤ 暦の知恵:なぜ「穀雨」みたいな名前があるの?

現代では、天気予報アプリで1時間先の雨まで予測できる便利な時代ですが、ほんの数百年前までは、そんなものは存在しませんでした。
人々は、空の色や風の匂い、鳥の動き、木の芽のふくらみなど、小さなサインを頼りに、次の季節を読み取っていたのです。そして、その自然のサイクルを「言葉」にしたのが、二十四節気の知恵です。
「穀雨」という言葉も、単に“雨が降る時期”というだけではありません。「穀物が潤い、育ちやすくなる時期だよ」と教えてくれる、自然のメッセージのようなもの。
このように、二十四節気には「自然と共に生きるためのヒント」が込められているのです。
ちなみに、穀雨の次には「立夏(りっか)」がやってきます。つまり、穀雨は“春の最終章”。この時期を境に、空気や日の光に「夏の気配」が少しずつ混ざりはじめるのも特徴です。
日本の季節感はとても繊細で、たった数日違うだけでも風景が変わることがあります。昔の人々がその移ろいに敏感だったからこそ、こうした豊かな表現が今に残っているのだと感じさせられます。
⑥ 小学生にもできる!穀雨のころの自然観察

では、実際にこの「穀雨」の時期、子どもと一緒にどんなことができるでしょうか?
おすすめしたいのが、「自然観察」です。といっても、特別な道具や知識は必要ありません。大切なのは、身の回りにある変化に気づこうとする気持ちだけです。
たとえばこんな観察ができます:
-
雨が降ったあとの地面や草のにおいを感じてみる
-
雨の音をじっと聞いて、「どんなリズム?」と話してみる
-
道ばたの草花が前の日とどう変わったかを見てみる
-
ツバメやカエルなど季節の生き物を探してみる
-
雨の日の公園の音・景色・においをメモに残してみる
写真を撮って記録するのもおすすめです。毎年、同じ場所・同じタイミングで写真を撮ると、「去年はここにタンポポが咲いてたな」「今年はちょっと早いね」といった自然のリズムが見えてきます。
また、おうちで雨の後に窓から外を眺めるだけでも十分な観察になります。葉っぱに残った水滴や、雨に濡れて色濃く見える木の幹、光の当たり方など、視点を変えるだけで多くの発見があるはずです。
こうした経験は、子どもだけでなく、大人にとっても「忙しさの中で忘れていた季節感」を取り戻すきっかけになるかもしれません。
⑦ 学校の授業や自由研究にもつながる!

穀雨の時期は、学校生活の中でもちょうど新しい学年に慣れ始めるタイミングです。この時期に自然に目を向けることで、理科や生活科の授業ともつながりが出てきます。
たとえば、小学2年生では「生きものの観察」や「植物の成長」などが学習テーマになります。タンポポやチューリップ、キャベツなどを育てる単元もあり、「雨がどうして植物の生長に大切なのか」「雨のあとの土や葉っぱはどうなっているのか」を実体験で知ることができます。
高学年になってくると、「気象のしくみ」や「水の循環」なども学ぶようになります。「穀雨」という自然の現象と言葉が、どうして昔の人たちの暮らしに必要だったのかを調べたり、雨の役割について自分なりにまとめてみたりするのも自由研究のテーマとしておすすめです。
たとえば、こんな問いかけからスタートすると良いでしょう:
-
「穀雨のころの雨って、いつもとちがうの?」
-
「田植えってなぜこの時期に始まるの?」
-
「雨がふると、なぜ植物がぐんぐん育つの?」
こうした疑問をもとに、自分の暮らしや観察、インターネットや図書館の資料を使って答えを探していくプロセスは、思考力や表現力のトレーニングにもなります。
さらに、二十四節気の他の名前もあわせて調べてみると、「小満(しょうまん)」や「芒種(ぼうしゅ)」など、どれも自然と人の暮らしを結びつけるヒントになっていることがわかります。
学校の中でも、家庭でも、日々の暮らしにこうした“気づきの種”を取り入れていくと、教科書の内容がもっと身近に、そして意味あるものに感じられるはずです。
⑧ まとめ:穀雨から自然と心をつなぐ時間へ

春の終わりに訪れる「穀雨」は、ただの雨の季節ではありません。そこには、「自然の恵みを待ち、育て、つないでいく」という日本の暮らしの知恵が込められています。
小学生のお子さんといっしょに、この時期の自然の変化を見つけたり、名前の由来を知ったりすることで、「なんでだろう?」という好奇心が育ち、「季節って、ちゃんと意味があるんだ」と気づくきっかけになるかもしれません。
そして、それは大人にとっても同じです。
忙しい毎日のなかで、ふと立ち止まり、雨の音に耳をすませる。地面の小さな芽や、戻ってきたツバメの姿に目をとめる。そんなひとときが、私たちの暮らしにささやかなゆとりと彩りを与えてくれるのではないでしょうか。
「穀雨」は、自然と人、そして心をつなぐ大切な時間。
今年はぜひ、親子でこの時期を楽しみながら、「自然のリズム」に耳を傾けてみてください。
✨関連記事はこちら⬇️