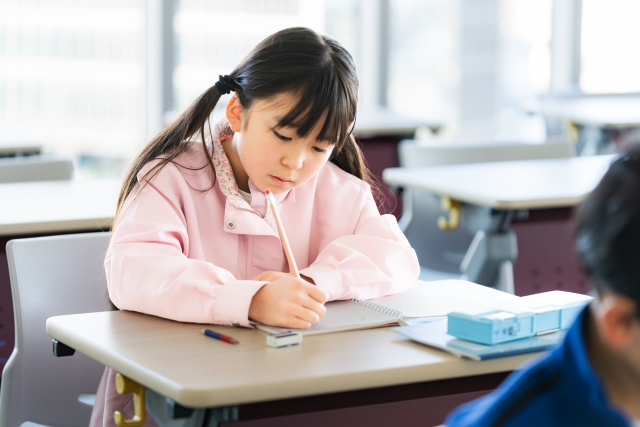 こんにちは。晴田そわかです。
こんにちは。晴田そわかです。
今回の記事では《国語の授業が盛り上がる!小学生向けアクティビティゲーム10選》について紹介させて頂きます。
- 1. はじめに
- 2. 小学生向け国語アクティビティゲームの選び方
- 3. 国語の授業が盛り上がる!小学生向けアクティビティゲーム10選
- 4. アクティビティを効果的に使うコツ
- 5. まとめ
- 6. よくある質問(FAQ)
1. はじめに
小学生の国語の授業で、「もっと楽しませたい」「集中力が続かない」「子どもたちが言葉に興味を持たない」と感じたことはありませんか?
そんな時におすすめなのが、国語の力を楽しく伸ばすアクティビティゲームです。遊びの要素を取り入れることで、子どもたちは言葉や文章に自然と親しみをもち、語彙力や表現力がぐんぐん伸びていきます。
この記事では、小学生向けの国語アクティビティゲームを10種類ご紹介します。どれも教室や家庭ですぐに使えるものばかりで、学年や目的に応じてアレンジ可能です。国語の授業にメリハリをつけたい先生や、家庭で学習をサポートしたい保護者の方にも役立つ内容となっています。
✨関連記事はこちら👇
2. 小学生向け国語アクティビティゲームの選び方
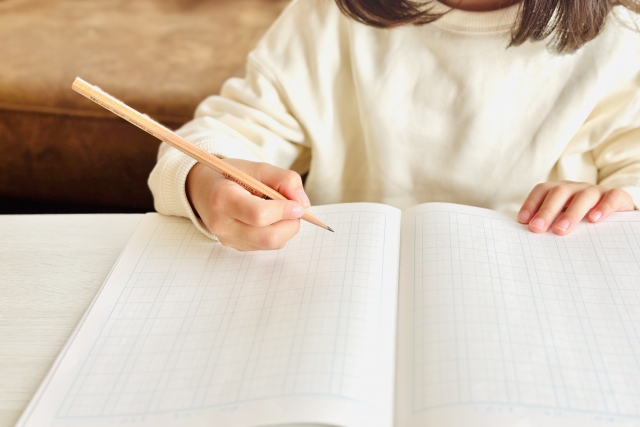
国語ゲームと一口に言っても、その種類や目的はさまざまです。以下のポイントを押さえて選ぶことで、より効果的に授業や学習に活かすことができます。
◆ 対象年齢を意識する
低学年は遊び要素が強めの簡単なルールが適し、高学年では思考力や語彙力を活かしたゲームが好まれます。
◆ 学習目標で選ぶ
-
語彙力を伸ばしたい → しりとり、かるた
-
表現力を育てたい → 作文ゲーム、セリフづくり
-
聞く・読む力を高めたい → 読み聞かせクイズ、順番直しゲーム
◆ 活動人数に注目
-
全体で盛り上がる → グループ対抗戦やリレー形式
-
静かに集中したい時 → 個人ワーク型やペア活動
◆ 授業時間に合わせる
-
5分〜10分で終わる導入用
-
15分以上かけて深める発展用
このように目的に合ったアクティビティを選ぶことで、遊びながら本格的に国語力を育てることができます。
3. 国語の授業が盛り上がる!小学生向けアクティビティゲーム10選
それではいよいよ、小学生の国語授業が盛り上がるアクティビティゲームを10個ご紹介します。どれも簡単に始められて、繰り返し活用できるゲームばかりです。
3-1. しりとりバトル(語彙力・スピード力)

対象学年:全学年(低〜高)
学習目的:語彙力の増強、言葉の瞬発力
● 準備物:
ホワイトボード、タイマー(なくてもOK)
● ルール・やり方:
-
クラスを2〜3チームに分けます。
-
最初の言葉(例:「さくら」)を先生が出します。
-
各チームが順番に、最後の文字から始まる言葉を5秒以内に出していきます。
-
同じ言葉は使えません。
-
時間切れ・ルール違反(例:んで終わる、知らない言葉)は失格。
-
最後まで残ったチームが勝ち。
● ポイント・指導のコツ:
-
低学年は「動物しりとり」「食べ物しりとり」などテーマを限定すると◎。
-
高学年は「漢字で書ける言葉限定」など、難易度アップも可能。
-
最後に出た言葉を使って短文作文をすることで、表現活動にもつなげられます。
3-2. 漢字ビンゴ(漢字の復習)
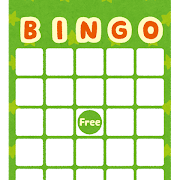
対象学年:中学年〜高学年
学習目的:漢字の定着・語彙力の復習
● 準備物:
-
ビンゴカード(5×5マス程度。空欄でもOK)
-
漢字の一覧表(教科書や習得済みの漢字から)
● ルール・やり方:
-
生徒は事前に自分のビンゴカードに好きな漢字を記入します(例:25個)。
-
先生は用意した漢字カードやくじで1つずつ漢字を読み上げます。
-
当てはまる漢字があればマスを塗りつぶします。
-
タテ・ヨコ・ナナメいずれか1列揃えば「ビンゴ!」
● ポイント・指導のコツ:
-
出題の際、読み方だけでなく意味や使い方もクイズ形式にすると効果大。
-
高学年には「四字熟語ビンゴ」や「部首ビンゴ」などもおすすめ。
-
授業の最後やテスト前の総復習にぴったりです。
3-3. 絵しりとり or 絵カード作文(表現力・創造力)
対象学年:低学年〜中学年
学習目的:語彙と表現力の融合、想像力の育成
● 準備物:
-
白紙のカード(A6サイズ)
-
色鉛筆・クレヨン
● ルール・やり方(絵しりとりの場合):
-
1人ずつ、前の人の絵を見て、それを言葉にし、次の言葉を絵で描きます。
-
最後に全員で絵のつながりを言葉にして発表します。
● ルール・やり方(絵カード作文の場合):
-
教師または子どもたちが描いた「絵カード」を数枚ずつ配布。
-
その絵に合う短文やストーリーを作って発表。
-
個人またはグループで話し合って構成してもOK。
● ポイント・指導のコツ:
-
絵と言葉を結びつけることで、文章表現に抵抗のある子も楽しく参加できます。
-
「何が描かれているのか」ではなく、「どう見えたか・どう感じたか」に着目することで、子どもたちの個性が光ります。
-
絵から発展して短編作文を書く活動にもつなげられます。
3-4. ことわざかるた(ことわざ理解)
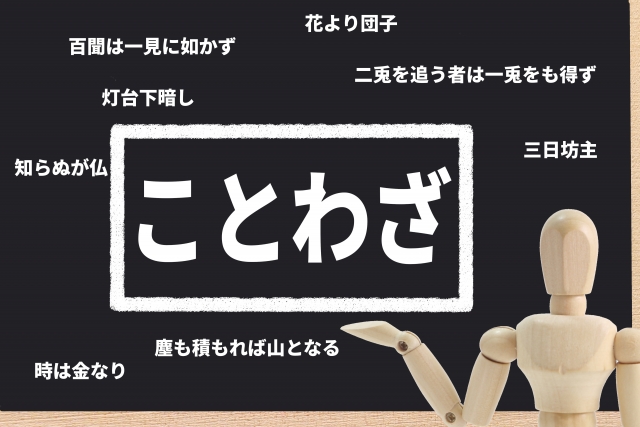
対象学年:中学年~高学年
学習目的:ことわざの意味理解と定着
● 準備物:
-
ことわざの「上の句(前半)」と「下の句(後半)」を書いた手作りかるたカード(例:表「犬も歩けば」/裏「棒に当たる」)
● ルール・やり方:
-
子どもたちを2人1組にして対戦形式にします。
-
読み手(教師または児童)が「上の句」を読み上げます。
-
「下の句」が書かれたカードの中から正しいものを素早く取った人が勝ち。
-
多くの札を取った方が勝者となります。
● 指導のコツ・発展:
-
最初は「絵付き」のカードを用意すると視覚的に覚えやすいです。
-
正解した後は、そのことわざの意味や使い方を発表させることで定着を図れます。
-
高学年では「新ことわざ作り」など発展活動にも挑戦可能。
3-5. 読み聞かせクイズ(聞く力・読解)

対象学年:全学年
学習目的:聴解力、要点をつかむ力、記憶力
● 準備物:
-
絵本または短い物語(学年に合った内容を選ぶ)
-
問題用紙(選択式または記述式)
● やり方:
-
教師が物語をゆっくり・感情を込めて読み聞かせます。
-
読み終えたら、内容について数問のクイズを出題(例:「主人公の名前は?」「最後に何をした?」)。
-
個人またはグループで答えを出していきます。
● ポイント・アレンジ:
-
グループ対抗戦にすると盛り上がります。
-
正解だけでなく「なぜそう思ったのか」まで考えさせると読解力が育ちます。
-
難易度調整がしやすく、朝の読み聞かせ時間にも最適です。
3-6. つなげて作文リレー(文章構成・発想)

対象学年:中学年〜高学年
学習目的:文章のつながり、表現力、協働力
● 準備物:
-
ノートまたはB4用紙
-
タイマー(任意)
● やり方:
-
5人ほどのグループをつくります。
-
1人目が書き出しの文(例:「ある日、森の中で…」)を書きます。
-
次の人は前の文を読んで続きの1文を書く、を繰り返します。
-
最後まで回して、1つの物語を完成させます。
-
完成したら全員で読み上げ発表!
● 指導のコツ:
-
「登場人物・場所・起承転結を入れよう」と事前にポイントを伝えると構成力が育ちます。
-
「○文以内」など制限を設けると集中力が増します。
-
想像力が広がり、ユーモアあふれる展開になることも多く、クラスで大笑いに。
3-7. 漢字探しレース(教室内アクティビティ)
対象学年:全学年(特に中学年向け)
学習目的:漢字の読み・意味理解、チームワーク
● 準備物:
-
教室内に貼る漢字カード(例:「森」「速」「思」など)
-
ワークシート(お題と記入欄つき)
● やり方:
-
教師が「意味」だけを読み上げます(例:「木がたくさん生えている様子」→「森」)。
-
子どもたちは教室内を探し、該当する漢字カードを見つけます。
-
自分のチームのシートに正しく書き写します。
-
制限時間内にいくつ見つけられるかを競います。
● ポイント・アレンジ:
-
チームで分担して探すことで協力性が育ちます。
-
カードはあえて難読な位置に貼ると運動にもなります。
-
漢字の使い方を文で説明させるとより深い理解につながります。
3-8. セリフを考えよう(会話文・感情表現)

対象学年:中学年〜高学年
学習目的:感情表現、会話文、表現力
● 準備物:
● やり方:
-
提示されたイラストを見て、「この時この子は何を言っている?」と想像してセリフを書く。
-
グループで発表し合ったり、劇にしてみたりする。
-
全体で「感情」「言葉づかい」などを意識して振り返る。
● 指導のコツ:
-
気持ちが分かりやすいイラストを用意すると取り組みやすいです。
-
文末表現(〜ね、〜よ、〜かな)を工夫させると実用的な力になります。
-
「おもしろセリフ部門」「優しさが伝わる部門」などで表彰しても◎。
3-9. 似ている言葉さがし(語彙の幅)
対象学年:全学年
学習目的:類義語の理解、語彙力アップ
● 準備物:
-
お題の言葉リスト(例:「走る」「大きい」「楽しい」など)
-
ワークシートまたはホワイトボード
● やり方:
-
教師が「お題の言葉(例:大きい)」を出します。
-
子どもたちは、それと似た意味の言葉をできるだけたくさん書き出します。
例:「でっかい」「広い」「巨大な」「広大」など。 -
個人戦・グループ戦どちらでもOK。
● ポイント:
-
国語辞典を使って調べながら進めることで、辞書引き学習にも。
-
「使い方の違い」「場面ごとの違い」などに触れると表現の幅が広がります。
3-10. 文の順番を直そうゲーム(論理的思考)

対象学年:中学年〜高学年
学習目的:論理的な構成力、読解力
● 準備物:
-
バラバラにした文(例:「彼は走った」「急いでいた」「電車に間に合いたかった」など)
-
文カードまたはワークシート
● やり方:
-
バラバラにされた文を配ります。
-
子どもたちはその文を「意味が通る順番」に並べ替えます。
-
結果を発表して、全体で答え合わせをします。
● 指導のコツ:
-
「理由→行動→結果」など、基本的な構成の流れを意識させる。
-
書き換え問題に発展させると、記述力も養えます。
4. アクティビティを効果的に使うコツ

◆ 「目的」を明確にして取り入れる
語彙を増やしたいのか、表現力を伸ばしたいのか、目的を明確にすることで活動の意味が深まります。
◆ 勝ち負けより「参加の楽しさ」を大切に
競争心は学びの原動力になりますが、負けて落ち込む子もいます。「参加することの楽しさ」に焦点を当てる声かけを大切にしましょう。
◆ 学年や学習状況に応じてルールを調整
1年生にはルールを簡単に、高学年には内容を難しく。柔軟にルールを変えることで、どの子も活躍できます。
◆ 振り返りや発表の時間を設ける
活動の最後に「気づいたこと」「おもしろかった言葉」などを共有させることで、学びが深まります。
5. まとめ
国語の授業は、「言葉っておもしろい!」「もっと話したい、書きたい」という気持ちを育てる場です。
今回紹介したアクティビティは、すぐに使えるものばかり。ぜひ、授業や家庭で取り入れてみてください。
遊びながら学ぶ国語活動は、学びと楽しさをつなげる最強の方法です。
6. よくある質問(FAQ)
Q. 1人でもできる国語アクティビティはありますか?
→「似ている言葉さがし」「セリフづくり」などは個人でも取り組めます。作文や日記に応用しても◎。
Q. 国語アクティビティを家庭で行うポイントは?
→「楽しみながら」がキーワード。ゲーム感覚で褒めながら進めると効果的です。
Q. 高学年でも盛り上がるゲームはどれ?
→「作文リレー」「順番直しゲーム」など、論理力や創造力を使う活動が特におすすめです。
✨関連記事はこちら👇